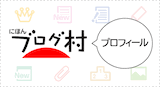備忘録 Siril 1.4.0 操作手順(スクリプト編)

2026.02.14 追記 ブログを移籍したため、この記事は更新が止まっています。 Siril 1.4系統のアップデートに伴う更新は下のリンク先で行います それでは Siril 操作手順のスクリプト編になります。 前回 は「自動前処理編」と言いましたが、「スクリプト編」とした方が良い内容になってきたのでタイトルを変えました。 Siril スクリプトを使用方法についてのブログはそこそこありますが、スクリプトの中身を扱うブログは少ないと思います。 スクリプトは自分向けにカスタマイズすれば利便性が格段に上がりますが、GUI操作に比べてハードルは高めです。 と言うことで、簡単ですがスクリプトの解説を含めた内容にしました。 備忘録と銘打っていますが、二の足を踏んでいた人の背中を押すことが出来たら嬉しいです。 なお、本ページで記載しているスクリプトはSiril公式のスクリプトを元に、tomが非公式に改良したものです。 元スクリプトの配布元は下記のリンク先にあります。 元のスクリプトは GNU General Public License v3(GPL v3) に基づいて公開されており、自由に利用・改変・再配布が可能です。 ただし、再配布の際には同じライセンスを適用する必要がありますので、私の改良版もまたGPL v3に基づいて公開しています。 著作権は元スクリプト作者である Cyril Richard氏に帰属します。 改良後のスクリプトになります。 あくまでも「tomが使っているスクリプト」の備忘録なので、もっと良い方法があるかもしれません。 こういうやり方もあるんだ程度の軽いノリで読んで頂ければと思います。 Siril のバージョンは1.4.0 beta2です。 追記:Siril 1.4.0 までのUI変更等に対応して画像などを差し替えています。 前提は前回から太字の所を加えます。 ・ベイヤー構造のカラーカメラで撮影した画像 ・ダークフレーム、 フラットフレーム 、ライトフレームがある ・ディベイヤーではなく、bayer drizzleを使う バイアスについては、バイアスフレームではなく合成バイアスを使っています。 撮影条件によってバイアスフレームを準備するのも大変なので、条件を変えて撮影したバイアスフレームから合成バイアスを算出します。 算出についても説明します。 その後、...