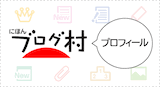IC2177 かもめ星雲

今回は久しぶりに撮影だけの記事です。 本当は先週(1/17頃)撮影したかったのですが、黄砂と薄雲のダブルパンチで空が真っ白に… 天気予報的には晴れで期待していたのに残念。 悶々としていましたが今週も晴れ予報! 連日の寒波の強風で色々と吹き飛んだのか、くすんだ空もスッキリしました。 先週とは比較にならないコンディション。 寒いけど期待しながら準備を進めます。 当初はバラ星雲の撮り増しを予定していましたが、低空までスッキリしています。 バラ星雲より暗めで低空にあるかもめ星雲が狙えるかも! という事で人生初のかもめ星雲です。 次の日も仕事だったので夜更かしは 厳禁 。 いつもなら光害軽減の為に9時過ぎまで待機してから撮影する所を前倒しで撮影開始。 30秒×210枚とフラットフレームを確保して23時頃には撤収完了! 寝ている間にSirilがスタック処理を終わらせます。 機材:SE102, ZV-E10未改造, QBP, AZ-GTi経緯台モード 条件:ISO1250, 30s露光×210枚 処理:トリミング、SPCC、AI デノイズ&デコンボリューション (object) あり バラ星雲より暗いだけあって、想像通りですが暗かった(笑) とは言え、未改造のエントリークラスのミラーレスでここまで写れば充分かな。 むしろ、 天体CMOSカメラが無くても ミラーレスでここまで写せるよ! と言えるのは大きいかも。 天体撮影の敷居が下げられると思います。 私は年内に天体用CMOSカメラを買って戦力アップする予定なので、ビフォーアフターが楽しみです。