備忘録 Siril 1.4.0 操作手順(手動前処理編)
2026.02.14 追記
ブログを移籍したため、この記事は更新が止まっています。
Siril 1.4系統のアップデートに伴う更新は下のリンク先で行います
最近は撮影が全く出来ないので、Sirilについての記事ばかりになってきました。
いろいろ触って使い方にも慣れてきたので、Sirilの操作手順を備忘録的な感じでまとめたいと思います。
あくまでも「tomが行っている処理方法」の記録で、Sirilのバージョンは1.4.0 beta2です。
追記:Siril 1.4.0 でも問題ない事を確認済みです。
今のところは手動前処理編、自動前処理編、加工編の3部作になる予定です。
インストールの前に
まずはインストール時のちょっとしたポイントです。
edgeでダウンロードすると下のアラートが出ますが、Sirilに関しては問題ありません。
もっと見るから保持を選びます。
単純に使っている人が少ないので「このソフト大丈夫?」と聞かれているだけです。
使用者が少ないという事は安全性の確認が出来ているか怪しいので、このアラートで一旦立ち止まらせる機能です。
びっくりしますし面倒ですが、安全には変えられません。
私は良いセキュリティ機能だと思います。
こういうアラートが出た場合は、インストールする前にセキュリティソフトでスキャンすれば、ウイルスに感染するリスクを下げられると思います。
では無事にインストールが終わったとして前処理を始めたいと思います。
今回は下記3点の前提で進めていきます。
特に1.4.0の新機能であるbayer drizzleを使うところがポイントです。
・ベイヤー構造のカラーカメラで撮影した画像
・ダークフレームとライトフレームがある
・ディベイヤーではなく、bayer drizzleを使う
フラットとバイアスは次回の自動処理編で話をしようと思います。
マスターダーク作成
画面左上のホームボタンを押し、撮影したファイルがあるフォルダを指定します。
まず、撮影した画像ファイルを、sirilで処理するfitsファイルに変換します。
同時にシーケンスファイルというモノも作成されるのですが、これがSirilの前処理にとって必要です。
最初からfitsファイルの場合もシーケンスファイルを生成する為に行ってください。
画面右上の変換タブをクリックします。
「+」ボタンを押して、撮影したダークフレームを全て選択します。
シンボリックとディベイヤーのチェックを外し、シーケンス名を入力します。
今回はダークフレームなので、dark にします。
コンバートをクリックすると、fitsファイルを変換してシーケンスファイルが生成されます。
次に、ダークフレームをスタックしてマスターダークにします。
重ね合わせのタブをクリックします。
methodは「average stacking with rejection」
Normalisaitonは「正規化なし」
pixel rejectionは「sigma clipping」で標準偏差の低・高ともに3.0で設定します。
ファイル名を決めて重ね合わせ開始をクリックし、処理が終わるまで待ちます。
これでマスターダークが完成しました。
ライトフレームの前処理
ダークフレームの時と全く同じ操作で、撮影した画像をfitsファイルに変換します。
ライトフレームなので、今回はシーケンス名をlightにしました。
続いて、ダーク減算を行います。
Calibrationタブをクリックします。
Darkを使用にチェックを入れ、フォルダマークをクリックして先ほど作成したマスターダークのファイルを指定します。
cosmetic correctionはチェックを外します。
ただし、ホットピクセルが多いカメラと分かっている場合や、後で行う位置合わせがうまく行かない場合はチェックを入れてください。
詳細は過去の記事参照。
ディベイヤーのチェックを外してStart Calibrationをクリックし、処理が終わるまで待ちます。
(bayer drizzleを使わない場合は、このディベイヤーにチェックを入れます)
これでダーク減算が完了しました。
pp_lightというファイルがダーク減算後の画像です。
続いて星の位置合わせとをbayer drizzleを行います。
整列のタブをクリックします。
DSOを撮影している場合は「global star alignment」を選択します。
惑星や月などの場合は「image pattern alignment」です。
ここはほとんどデフォルトのままでよいと思いますが、念のため「use drizzle」が青色になっている事、scalingとpixel fracionがどちらも1.0になっている事を確認します。
そして、整列開始をクリックして処理が終わるまで待ちます。
r_pp_ligthという名前のファイルが生成します。
処理が終わった後、グラフのタブをクリックすると下のようなグラフが出てきます。
各フレームのfwhmを表したグラフです。
1フレームだけ大きくブレたりした画像をスタッキングから除外することが出来ます。
ですが、私はこの機能は使っていません。
後述しますが、スタック時にfwhmの数値に従って重みづけを行っているため、自動的にfwhmの大きなフレームの寄与は小さくなるためです。
ここまでくればあと一息、最後のスタッキングを行います。
重ね合わせのタブをクリックします。
methodは「average stacking with rejection」
Normalisaitonは「additive with scaling」
pixel rejectionは「MAD clipping」で標準偏差の低・高ともに3.0で設定。
weightingは「weighted FWHM」を選択します。
bayer drizzleを使用する場合はMAD clipを奨励すると公式が言っています。
また、ここでweighted FWHMを選択する事で、fwhmの大きなフレームの寄与を小さくしつつ、スタッキング枚数を稼ぐ事ができます。
さらに、stacking resultは3か所全部にチェックを入れ、出力するファイル名を入力します。
この時、上書きにチェックが入っている事を確認します。
チェック無しの状態で同一フォルダ内に同じ名前のファイルが存在している場合、ファイルが保存されません。
これで「重ね合わせ開始」をクリックして終わるまで待ちます。
結構長いです。
これで前処理は完了です。
出来上がった画像はストレッチなどの加工を行います。
処理が終わった後で「設定を間違えてしまった」、「別の処理方法を試してみたい」という場合にはシーケンスファイルが役立ちます。
その他
処理が終わった後で「設定を間違えてしまった」、「別の処理方法を試してみたい」という場合にはシーケンスファイルが役立ちます。
ここまでで生成している画像&シーケンスファイルの名前の説明をします
light … raw画像から変換したファイル
light … raw画像から変換したファイル
pp_light … calibration(ダーク減算)を行ったファイル
r_pp_light … 整列(位置合わせ と bayer drizzle)を行ったファイル
r_pp_light … 整列(位置合わせ と bayer drizzle)を行ったファイル
もう1度スタッキングを別の設定でやり直したいという場合は、画像シーケンスのタブからr_pp_lightというシーケンスを選択すれば、整列が終わった状態に戻ります。
同様に整列からやり直したいという場合はpp_lightを選択してください。
なお、そのまま実行するとファイルが全部(画像もシーケンスファイルも)上書きされてしまうので注意です。
特に重ね合わせの出力ファイル名を同じにしてしまうと、前の画像が上書きされてしまうので比較すら出来なくなってしまいます。必ず出力ファイル名を設定してください。
(かといって上書きのチェックを外すと、同一フォルダ内に同じ名前のファイルがあると保存されません)
こんな感じで手動前処理編は終了です。
(かといって上書きのチェックを外すと、同一フォルダ内に同じ名前のファイルがあると保存されません)
こんな感じで手動前処理編は終了です。
が、毎回こんなことを手動でやるのは正直めんどくさいです。
一旦処理を開始したら、終わりまで一気に進めたいですよね。
という事で、次回はこれらの処理をスクリプトで実行する方法になります。











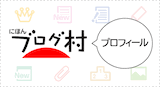
コメント
コメントを投稿