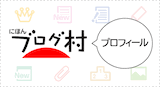Siril 1.4.0 でGaia DR3をローカルにインストールする方法

Siril 1.4.0 からSPCCが使えるようになっています。 色合わせが確実に出来るので重宝しています。 26.1.9 追記 Siril 1.4.1 リリースにより不具合が解消しました。 下記の操作を行わなくてもオンラインでSPCCが出来るようになっています。 ただし、2025年末頃から不具合が発生しており、デフォルトの設定のままではSPCCが動きません。 このエラーはSirilが起動した時のコンソールに出てくる注意書きにも書かれています。 AIで翻訳すると… Gaia アーカイブは現在「利用可能」と表示されていますが、SPCC で使用する際には依然として問題が発生しています。 Siril が送信している URL 形式は変更されておらず、Gaia アーカイブのヘルプデスクも「そちら側でも何も変更していない」と報告しているため、原因は不明です。 私たちは現在、この問題の原因を調査し、修正または代替手段の実装に取り組んでいますが、Gaia アーカイブの挙動が以前の状態に戻らない限り、当面の間、リモートカタログは SPCC では使用できないと考えるのが最善です。 少なくとも バージョン 1.4.1 までは(現時点でリリース時期未定) 使えない見込みです。 したがって、現時点ではローカル SPCC カタログをダウンロードして使用してください。 という事で、現段階ではSPCCを利用するにはGaia DR3のデータをローカルにダウンロードする必要があります。 インストーラーはSiril側で準備しているので、操作は簡単です。 が、気をつけないと正常に動かないポイントがあったので今回はそのやり方をまとめます。 Gaia DR3のインストール スクリプト → python スクリプト → core → Siril Catalog Installerの順に進みます。 すると下の画面が出てきます。 (初回はライブラリのインストールなどで起動に少し時間がかかるかもしれません) 上の方に「Astrometory Catalog」のインストールボタンがありますが 無視 します。別のデータです。 これをインストールしてしまって、(当然ですが)SPCCが動かないというトラブルの報告が海外の掲示板にいくつかありました。 SPCC Catalogに値を設定して進めていきます。 Observer L...