M8とM20とpythonスクリプト
またしても綺麗に晴れたので、撮影が捗ります。
M8とM20
少し前に工作してAZ-GTiにカメラを載せられるようにしたので、SEL55210で撮影してみました。
早速リザルトです。
機材:SEL55210(焦点距離210mm), ZV-E10未改造, QBP, AZ-GTi経緯台モード
条件:ISO1250, 30s露光×245枚
処理:トリミング、SPCC、AI デノイズ&デコンボリューション
ダブルズームキットのレンズとカメラ(未改造)、かつ光害地のベランダ撮影でここまで写れば文句はないです。
望遠鏡を買わなくてもここまで写せるのは少々驚きました。
エントリークラスの機種でもダブルズームキットを持ってる人なら経緯台とQBPフィルターを買うだけで星雲が写せる!
周囲に光害が少なければQBPすら不要ですし。
天体撮影って思ってたよりハードルが低かった。
望遠鏡が必須という思い込みがありましたが、むしろ経緯台さえあれば何とかなる事が分かりました。
ちなみに、QBPを使っているので三裂星雲の青色が苦しいと思っていましたが、ギリギリ何とか写りました。ぼんやりしていて青色と言えるレベルでは無いですが笑
また、エントリークラスの未改造カメラでこのレベルですから、天体用カメラを買うとどこまで綺麗になるのか楽しみです。
ただ、三裂星雲の右上に違和感があるので調べてみたところ、円形のゴースト(?)が出てしまいました。
スタックしただけの画像を思いっきり強調しています。
レンズの先にQBPフィルターを取り付けたので、レンズとフィルターが近すぎたせいかな?と妄想しています。
解決策が無いか、のんびり考えたいと思います。
これを撮影していて、200mm前後の鏡筒がたくさん出ている理由がちょっと分かりました。
複数の星雲が1枚に写るのってすごく良い。
やっぱりいろんな焦点距離の鏡筒が欲しくなってしまうんですね…
天文が沼と呼ばれる理由もホントによく分かりました。
pythonスクリプト
撮影ではない方のネタに移ります。
ここ最近は、あぷらなーとさん考案の処理法をSirilに実装しようと頑張っています。
前回悩んでいたseqcosme(cosmeのループ処理)を使用する方法からは一旦離れて、別の方法をとりました。
これでピクセルマッピングとクールファイル補正法の実装に成功しました。
左からスタックしただけ、ダーク減算+ピクセルマッピング適用、さらにクールファイル補正適用です。
ピクセルマッピングを逃れた赤矢印の所にあるノイズもクールファイル補正で消すことが出来ました。
やっと出来た…!これはうれしい。
cold_sigma = 0 にすると画面全体に発生している縮緬ノイズもかなり消えました。
その変わりにディテールも若干甘くなった気がするので、何を重要視するかで値を決める感じですね。
残るはコスミカット法だなと、満足感に浸っていたら違和感を感じました。
なんでホットピクセルのノイズが白色なんだろう?
普通、RGBのどれかの色だと思っているんですが…
星ナビ8月号を読む限りGのノイズが多かったので、本来Gになるべきノイズが白色になっている様に見えます。
同じ画像をdrizzleで処理すると、白色のノイズは無く、Gになっている事が確認できました。
スタックしただけの画像でも発生しているので、私がスクリプトでやらかしている可能性も低い。
もしや、Sirilのディベイヤーに何かがある?
ディベイヤーの計算法違いで調べてみるか…な…?苦笑
コスミカット法を検討した後で調べるかどうか考えてみます。
気にしなくて良い違和感である事を願っています。



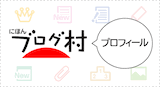
コメント
コメントを投稿