M16とpythonスクリプト
土曜の夜、風呂に入る前に外を見ると完全に曇っていて、撮影を諦めました。
が、風呂から上がってしばらくして、ふと空を見ると綺麗に晴れてる!
という事で急遽撮影しました。
狙いは前回ゴミで酷いことになったM16です。
早速リザルトです。
機材:SE102, ZV-E10未改造, QBP, AZ-GTi経緯台モード
条件:ISO1250, 30s露光×179枚
処理:トリミング、SPCC、AI デノイズ&デコンボリューションあり
処理ですが、GraXpert の deconvolution(stellar)は使っていません。
というのも、stellar で処理すると画像の外周ばかりが強烈に補正されてしまいます。
M17の時も悩みましたが、今回は避けようがないくらいに酷かったので採用出来ませんでした。
どうすれば外周だけでなく全体的に補正がかかるのか…
何か良い条件が無いか探ってみたいと思います。
GraXpertの不具合なら逆にありがたいくらい。
また、以前効果が無いと言った deconvolution の object ですが、めっちゃ効果ありました。
創造の柱がクッキリしました。
左がdeconolution(object)なし、右がありです。
意味無いと言ってスイマセン…これからはobjectも使います。
ただ、以前の検討だとこんなに分かりやすい変化は無かったので、何か違いがあるんでしょうね。
ちなみに、objectでも strength を上げすぎるとアーティファクトが出ます。
何事もやりすぎは良くないです。
下は strength = 0.8まで上げたら出てきました。
続いて、前回の最後にちょろっと書いたクールファイル補正法のpythonスクリプトです。
引き続き検討を進めています。
この記事を書いた後、あぷらなーとさんのXの投稿で「星ナビ8月号にノイズまみれの画像が付いてくる」と知る事ができたので、急いで購入して検証を始めてみました。
ノイズまみれの画像が手に入ると分かった瞬間に猛烈に喜んでしまいました。
で、画像をダウンロードして圧倒的なノイズを見たら、更に喜んでしまいましたw
ノイズに喜んでしまうあたり、いい感じにイカれてきた気がしています。
が、やはり実装は思うようにいきません。
ピクセルマッピングを適用した画像にクールファイル補正を適用しするのが難しかったです。
ピクセルマッピングだけ、クールファイル補正法だけを個別に実行するのであれば動くものの、両方を適用するのが難しい。
どう処理するかだけで結構悩みました。
更に、何とか処理フローは思いついたものの、実行させるにも一苦労です。
ある箇所でseqcosmeを使ってみたのですが、seqcosmeの実行中に必ずSirilがクラッシュしてしまうんです。
スクリプトを使わず、コマンド入力でseqcosmeを実行してもSirilがクラッシュするので、おそらくseqcosmeの不具合かなと想像しています。
seqcosmeを封じられてしまったので、cosmeを対象画像全てにループ処理するという力技で解決させました。
やっている事は同じなのですが、ちょっとスマートじゃない感じです。
これで何とかプログラムを走らせる事に成功しました。
解決かと思ったのですが縮緬ノイズが消えません。
前回、クールファイル補正法のプログラムが出来たと思っていましたが、検証してみると失敗していたというオチです。
左からスタックしただけ、ピクセルマッピング適用、クールファイル補正法の出来損ない適用です。
いやー、悔しい。
何が間違っているのか、見直しを進めていきます。
これが完成した後にはコスミカット法にも手を出していきたいのですが、これは恐らくSirilでは実装不可能だと思っています。
というのもステライメージでは96bitの画像処理空間を持っているらしいのですが、Sirilにそういう記載がない為です。
保存するデータとしては32bitしか持たないが、演算は64bitや96bitで行っているという嬉しい誤算に望みをかけてトライしてみる予定です。
が、まずはクールファイル補正法を何とかしないとダメですね。
何が間違っているんだろうなぁ・・・




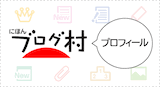
コメント
コメントを投稿