備忘録 Siril 1.4.0 操作手順 (加工編)
2026.02.14 追記
ブログを移籍したため、この記事は更新が止まっています。
Siril 1.4系統のアップデートに伴う更新は下のリンク先で行います
3部作最後の加工編になります。
スクリプト編の終盤にコメントしましたが、加工に関しては勉強中です。
特にストレッチが難しくて、ここ最近はGHSを練習していますが何が正解なのか正直よく分かりません…
まだまだ試行錯誤中なので、tomが使えている( = 素人でも比較的簡単に使える)ツールに重点を絞って進めていきます。
特にストレッチが難しくて、ここ最近はGHSを練習していますが何が正解なのか正直よく分かりません…
まだまだ試行錯誤中なので、tomが使えている( = 素人でも比較的簡単に使える)ツールに重点を絞って進めていきます。
1.4.0の新機能を使うため、SPCCとGraXpertを使用する形で進めます。
追記:Siril 1.4.0 リリースに伴って内容を一部修正しています。
主にUIの変更や仕様変更で生じた操作法の変更を反映しています。
GraXpertのインストール
siril 1.4.0の新機能のため、GraXpertをインストールしておきます。
記事作成時点ではGraXpert 3.1.0 rc2です。
リニア処理
スタッキングが終わった画像を読み込みます。
画面はほとんど真っ黒のままです。
右下にある「線形」を「自動イコライゼーション」に変えると撮影したものが見えます。
画像の内、必要な所をトリミングします。
(もちろん、画面全体を使う場合は必要ありません)
ここでGraXpert-AI.pyを起動させます。
Background Extractionを選択します。
Smoothingは0.2程度で良いと思います。
applyを押せば補正されます。
イマイチであれば戻るボタンで処理を取り消して数値を変更しやり直します。
続いてSPCCを実行します。
siril 1.4.0から導入されたSPCCは、画像の座標データが必須になります。
まず ツールから「天体測量」をクリックし、その先の「アストロメトリ」をクリックします。
siril 1.4.0から導入されたSPCCは、画像の座標データが必須になります。
まず ツールから「天体測量」をクリックし、その先の「アストロメトリ」をクリックします。
まずは望遠鏡の焦点距離をFocal lengthに、カメラの1ピクセルのサイズをピクセルサイズに入力します。
画像パラメータに撮影した天体の名称を入れ、findをクリックします。するとその下の枠に天体の名称が出てくるので、右下のOKを押します。
このウインドウが消えると座標データが取得できています。
たまに座標データが取得できない事がありますが、そうなった場合はSirilでの座標データ取得は絶望的です。私は解決できた事がありません。
処理を進めてからアストロメトリを実行すると失敗する印象が強いです。
スタック後の出来るだけ早いタイミングで実行すれば成功率が上がります。
座標データが取得できたらSPCCに移ります。
追記
2025年の末頃から不具合でSPCCがデフォルトの設定では動かなくなっています。
回避するための方法を記事にしたので参考にしてください。
追記終わり
画像処理の色補正から、「分光測光色補正」をクリックします。
私のOSCセンサーはZV-E10ですが、そんな選択肢は無いので適当なセンサーを選びます。
その下のDLSR low pass filterも同じく適当に選びます。
(一応APS-Cなので、APS-Cの中から選んでいるつもりです)
tomはQBPフィルターを使用しているのでOSC filterにQuad BPを選びます。
ただし、この方法ではSPCCで色合わせが出来たように見えますが、おそらく偶然色が合った様に見えるだけです。
というのも色合わせの結果として出てくるグラフに相関がイマイチなためです。
私の設定が悪い可能性もあるので、いずれ解決したいと思っています。
この後、GraXpert-AIに戻ります。
Denoisingを選びます。
Denoisingを選びます。
ここでもuse GPUのチェックを確認します(tomはCUDAが無いのでチェックを外します)
Applyを押すと処理が始まります。
画像サイズにもよりますが、結構時間がかかります。
続いてデコンボリューションです。
これはGraXpert 3.1.0 rc2の機能なので、安定版を使用している場合は使えません。
デコンボリューションはobjectsとstellarがあります。
星雲や銀河等はobjects、星はstellarに使うそうですが、
objectsもしっかり効果がありました。
stellerもobjectsも両方使ってよさそうだと思っています。
Strengthは0.2程度、SPFは8程度のから始めることが多いです。
満足がいくまで値を変更しながら調整します。
strengthが大きいと、星の色が変わってしまったり星の半分だけ処理がかかったりと、良くない結果になることが多いです。
控えめにするのが良いと思います。
これでリニア処理が終わりです。
ノンリニア処理
ここからストレッチに入ります。
GHSは難しいので、ヒストグラム変換で頑張ります。
まず、ピンクスターを回避の為に最も明るい星の輝度を飽和させます。
写真の中で大きめの輝星にマウスを合わせ、右下に表示されているRGBの値を調べます。
一番RGBの数字が大きくなる所を探して、この値の内で1番小さい値を覚えておきます。
上の画像だとGの24.619%です。
上の画像だとGの24.619%です。
ここで「自動イコライゼーション」を「線形」に戻します。
ヒストグラム変換の画面を開きます。
highlightsに先ほど覚えた数字を入力します。
先ほど覚えた数字は24.619%ですが、ここでは0.24619になります(なお、下二桁くらいは切り捨てて大丈夫です)
ここで適用をクリックする事で、星の輝度が飽和しました。続いて、歯車マークをクリックし、midtoneとshadowsの値を覚え、リセットを押します。
あとはshadowsとmidtonesに先ほど覚えた値を入れ、この2つの値を満足するまで調整します。
何故こんな手順なのかというと、歯車マークを押すと自動補正されますが、値が弄れなくなります。
その後の調整が出来ないので、自動補正の値をスタートとして好みの画像に仕上げるためにこのような手順にしています。
ポイントとしてはshadowsを上げれば上げるほど背景が暗くなりますが、やりすぎると暗いデータを削ってしまっています。
tomはshadow側のclipが1%くらいまでを上限にしています。
で、このヒストグラムを見ると分かる通り、Rのピークだけが左にずれています。
画像的にももう少し赤成分が欲しいので、赤だけを強調します。
緑と青の丸をクリックしてチェックを外し、midtonesを少し小さくします。
そうするとピークの山が右に動くので、GとBの山に重なるくらいの位置に調整し適用をクリックします。
tomは基本的にここで完成とし、jpgに保存しています。
Sirilにはもっと沢山の機能があり、まだまだ使いこなせていません。
のんびり勉強していこうと思っています。
いろいろ使いこなせる様になったら、今回みたいに投稿したいと思います。
これを書いている最中に、Siril 1.4.0 beta3のアップデートが配信されました。
どんどん改良されるので楽しみが尽きませんね。
そうするとピークの山が右に動くので、GとBの山に重なるくらいの位置に調整し適用をクリックします。
tomは基本的にここで完成とし、jpgに保存しています。
Sirilにはもっと沢山の機能があり、まだまだ使いこなせていません。
のんびり勉強していこうと思っています。
いろいろ使いこなせる様になったら、今回みたいに投稿したいと思います。
これを書いている最中に、Siril 1.4.0 beta3のアップデートが配信されました。
どんどん改良されるので楽しみが尽きませんね。
いつかはSirilのpython scriptを自作してみたいもんです。
最近はAIでコーディング出来るので、言語を知らなくても作れてしまう所が本当に良いですね。
自分の思いついた処理を実装する事のハードルが大きく下がっています。
追加したい機能が見つかれば挑戦してみたいと思います。


















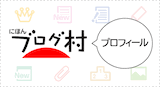
コメント
コメントを投稿