ノイズはどこから出てくる?
このノイズは一体何なんなのか?
パっと見はどう考えてもショットノイズです。
ただ、コンポジットの枚数に影響を受けている様に感じないんです。
今日は、その「感じ」が本当に正しいのか考えていきます。
先日撮影したM4の画像を、20枚コンポジットと120枚コンポジットで比べていきます。
ひとまずコンポジットを終えたばかり(自動イコライゼーションでストレッチ済み)の画像です。
右が20枚、左が120枚です。
えぇえぇぇぇ…右側のノイズが少なくなってる。
もしかして、この後の処理でノイズが増えている?
検証のため処理を続けていきます。
background Extraction後の画像です。
右が20枚、左が120枚です。
120枚コンポジットの方のノイズ感が増えました。
逆に20枚の方はノイズの増加量が少なく感じます。
が、よく見てみると球状星団の明るさが違っています。
自動イコライゼーションにチェックが入っているので明るさが変わったのでしょう。
と言うことは、この時にノイズも一緒に引き上げられているのか…?
ストレッチはGHSが難しいので、ヒストグラム変換からオートで行っています。
ストレッチが終わってから自動イコライゼーションをoffにしても見た目は変わらないので、ヒストグラムのオートは自動イコライゼーションと同じ機能だと思います。
つまり、せっかくコンポジットしてノイズを減らしても、ストレッチでノイズまで引き上げてしまっていたと言う事になりそうですね。
あー、よかった。
Sirilの処理を疑ってましたが、そんな事よりまず自分自身の知識と経験不足を考慮しないとダメでした(笑)
何にせよ、問題が解決出来そうでホントに良かった。
GHSって難しいですが、覚えるしかないね。
頑張ります。
GHSを覚えてから、今までの画像も全部処理し直しだな…
ここからは余談ですが、前回pythonのプログラムが狙い通り出来上がったので調子に乗ってしまいました。
pythonでダーク減算&フラット補正、位置合わせコンポジット、ディベイヤーまで出来るプログラムを作ってみました。
これでM10を20枚コンポジットしてみると…
いいシマシマ模様だ。おしゃれ~(笑)
更に、作った後でディベイヤーとコンポジットの順序が逆になってる事に気づきました。
何も分かってない素人がこんな事するから訳の分からないミスをするんですが、その程度の知識でもプログラムが出来てしまうcopilotは本当に凄い(結構複雑だったのでgeminiも使いました)。
画像処理の理論とpythonをもっと勉強すれば、自分好みの処理ソフトを作るのも夢じゃないなと思いました。
こっちもコツコツ勉強していきます。




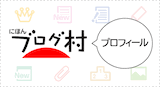
コメント
コメントを投稿